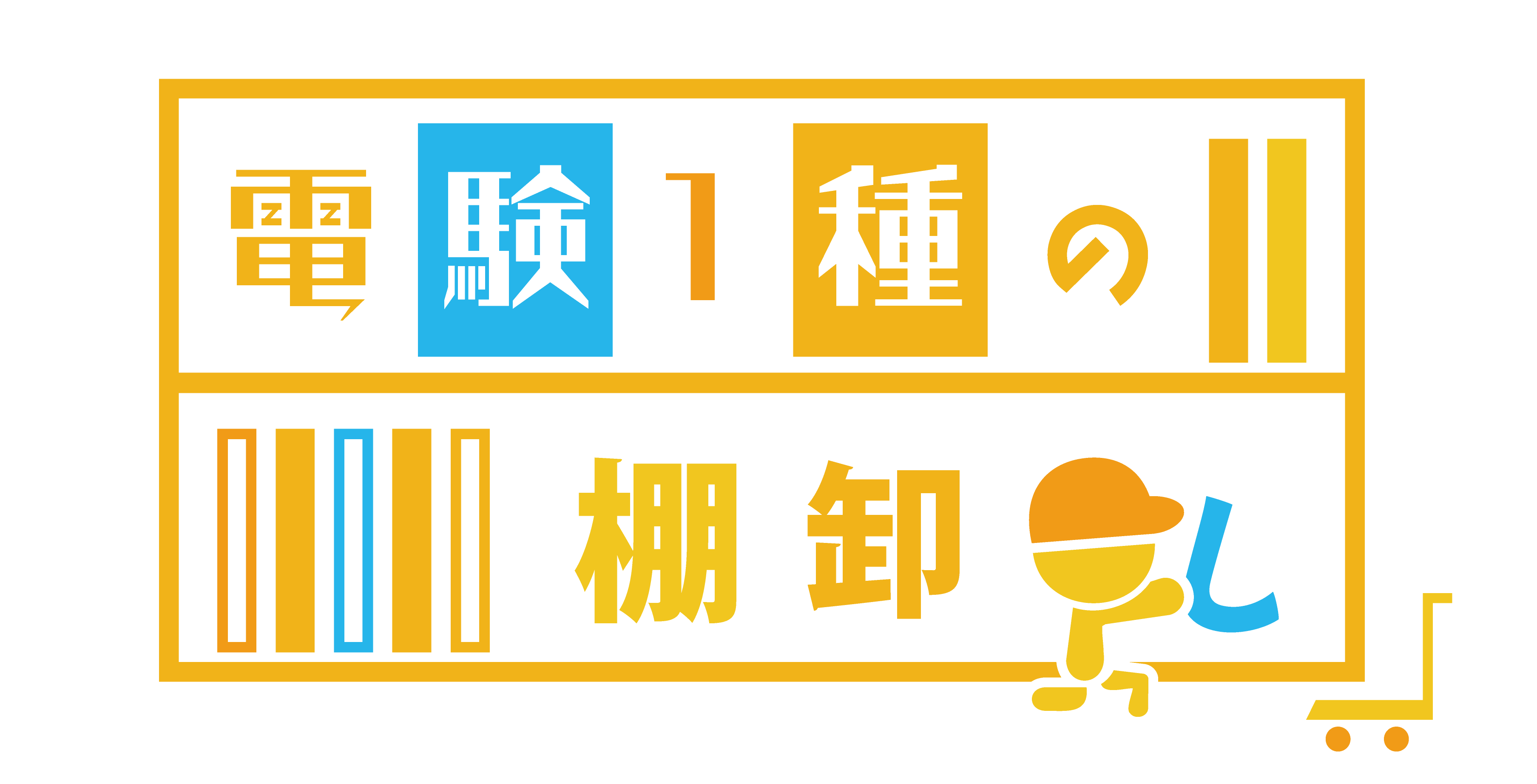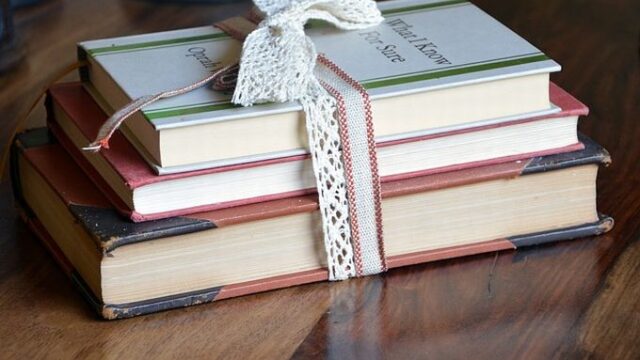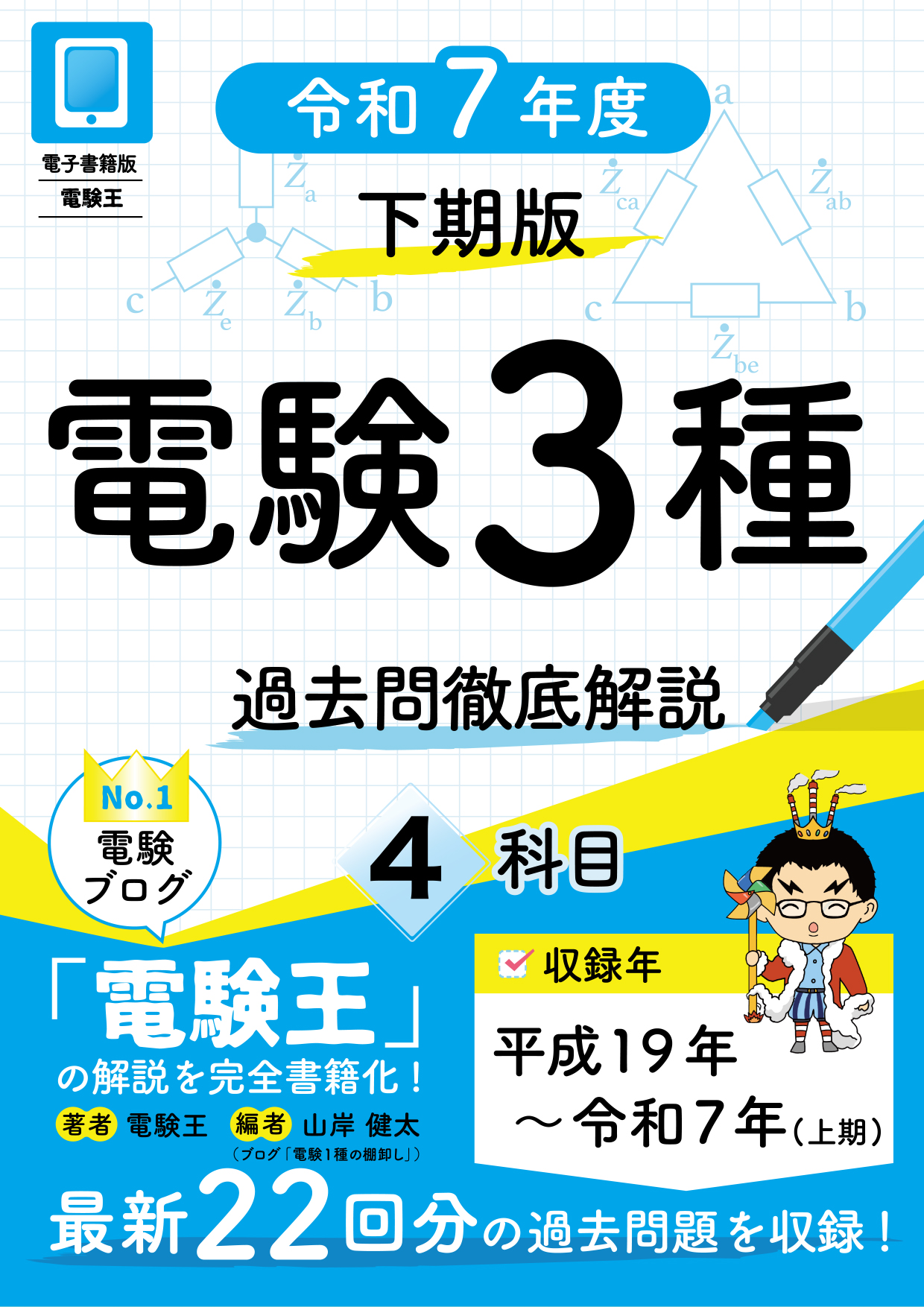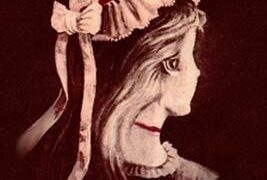皆さまお疲れさまです。ケンタ(@den1_tanaoroshi)です。
数ある電験3種の参考書のジャンルに最近、新しいシリーズが登場しました。電験3種のジャンルは参考書の種類が豊富ですが種類が多いのが悩ましい一方で、使いやすい参考書が出れば、ただそれを選ぶだけで合格に一歩近づきます。
ということで今回ご紹介する、とりあえず選んでおけば間違いない参考書は「みんなが欲しかった」シリーズです!
実は私はTAC出版ユーザーでした

タイトルにあるように、実は私はTAC出版ユーザーでした。公認会計士とか公務員試験で大手の資格学校のTACの出版部門です。過去形になっているのは別にTAC出版に見切りをつけたわけではなく、単に勉強していた資格試験に合格したからです笑
私が受験したのは非電気系民間試験である日商簿記2級でしたが、TACの参考書はキャラクターや図がたくさん使われていて解説が平易でしたので、まったくの門外漢にもかかわらず理解が進んだ記憶があります。
こういう経緯もありTAC出版には割とポジティブな印象を持っていました。そんな文系の資格試験本に定評のあるTAC出版が、今回は理系の電験3種の参考書を出したという情報を聞いたので、早速中身を見てみました。
シリーズの構成
TACの参考書は何と5冊構成になっています(!?)「4科目と電気数学だろ?」と思われた方、半分正解です笑
試験科目の4科目に加えてオリエンテーション本とで計5冊になります。
5冊とも
- カラー印刷であって、
- そのためカラフルなイメージ図が頭に残りやすい
というような構成になっています。特に動作を交えたイメージ図が豊富で、記憶の取っ掛かりができやすい作りになっています。
私が勉強していたときは、コロナ放電の様子などを空想で想像するしか無く、参考書とか問題の解説と矛盾しない範囲で想像するしかありませんでした。そういったことを↓の記事のように参考書の余白に書いてサイクルを回していたのですが、この参考書には最初から描いてありますし、間違いのない現象の描写となっていますので、ズレなくイメージが結べるようになればまず不正解になることは無いかと思います。

全体を通してはこんな感想を抱きました。次は個別に見ていきます。
電験3種 はじめの一歩

これはオリエンテーション本です。試験の概要とか勉強への臨み方とかが書いてあります。
- 会社からは受けろとは言われたけど、電験をどこからどうやって進めていけば良いのか分からない
- 自分は文系だから、全ての基礎と言われている理論科目がそもそも理解できるか心配
このどちらかに当てはまる人は取り敢えず読んでみて下さい。
私視点で今となって改めて読んでもなるほどなと、ストンと腹に落ちることが結構書いてあります。
特にそう思ったのは学習法についてです。ちょくちょく記事で私の学習のやり方を書いてきましたが、部分的にそれに近いことが書いてあって、読んでて納得感がありました。


また、オリエンテーション以外には各科目の基礎と電気数学が収録されています。電気数学の詳しい内容は
- 分数の計算
- 2次方程式
- 三角比
- ベクトル
- 複素数
- フェーザ表示
あたりです。電験3種に最低限必要な数学が網羅されていますので、高校数学の基礎が少し不安な方はピンポイントで学習してみるなり、理論科目を始めて数学が分からなくなってきてから使ってみるなりの使用方法があるかと思います。
逆に周りに電験受験者がたくさんいて情報が豊富であったり、数学にある程度自信がある方はこの本をスキップして問題は無いですね。
電験三種 理論の教科書&問題集
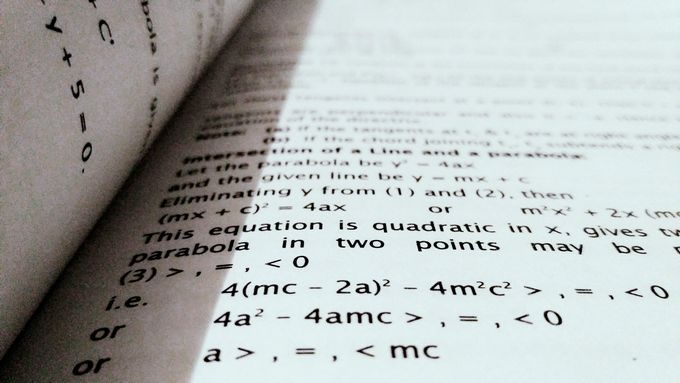
実物を手にとってみるとすぐに分かりますが、なんと法規科目版の2倍の厚さです笑 それだけ基礎科目として重要ということですね笑
正誤表を最初に出せる出版社の自信を感じました
ページを開いて最初の方に正誤表の案内があって、Webページの存在を知ることができます。このような参考書を最初に使えば「参考書というものには誤植があって、それを訂正しているWebページがあるものだ」という常識ができますね。
なにが言いたいかと言うと、「↓のような事態は避けられそうです」ということです!

早速、TACの本に誤植があるか調べてみたところ、第2版についていくつか誤植が見つかったそうです。
勉強スタイルに沿った本の工夫がある
本のタイトルが「教科書&問題集」となっているように、前半が教科書で後半が問題集となっています。これは、1冊の前半と後半で別れているということではなくて、教科書と問題集を物理的に切り離す事ができます!
簿記2級の時と同じようにTAC出版の参考書としては当たり前なのですが、電験の参考書としては珍しいタイプですね。
また、TACの方は、教科書の1単元が終わるごとに問題集に挑戦するような使い方が推奨されています。そういった使い方がしやすいように、教科書→問題集の移行がスムーズにできるようなマーク誘導もあります。
分からなかった問題が出たときは解説を見つつ教科書に戻る必要がありますが、そもそも2つを切り離すことができるため、問題集と教科書を見比べることが簡単にできます。
電験三種 電力の教科書&問題集

一般的に理論は新しい概念が次々と登場してくるのに対して、電力では例えば発電種別ごとにキーワードがたくさん登場してきます。ここで多くの参考書では、キーワードを文章の中にまぶして説明して終わりにしてしまいます。
一方でTACは、図を使って詳しく説明しています。特にキャビテーションの説明は秀逸でした!キャビテーションの説明だけに1.5ページも割いた参考書はこれまでになかったはずです。他にもニードル弁の役割を動作を交えて説明したり、何番煎じかの参考書とは到底言えないです。
また、執筆者の方は鉄塔マニアなのかというくらい、がいしや電線などを含めた鉄塔の絵が本物っぽいです。難着雪リングがあるときの雪の付き具合まで説明しているとは思いませんでした。

電験三種 機械の教科書&問題集

機械は計算問題が多く、例えば三相モーターは原理をきちんと理解していなくても何となく得点できるところがあります。何を言いたいかと言うと、この参考書を書いた人は本当にきちんと理解されていて、自分が如何に理解していなかったかが分かりました。
せめて、三相誘導機と三相同期機の部分だけでも勉強し直したくなりました…三相同期機の原理→始動法→トルク→負荷角の一連の説明は、私が知らない考え方も出てくる流れでしたが、ストーリー性があってなるほどなと思う内容でした。
電験三種 法規の教科書&問題集

学習マップで各科目・各単元の相関を可視化している
他の科目間との単元相関マップがあり、これがあることで俯瞰的に頭の整理がしやすいです。色んな参考書を見てきましたが、これはTACが初めてではないでしょうか。
私のブログでも実は描こうとしていた経緯があるのですが、あまりに単元数が膨大でかつ正確性がいる作業でしたので、断念した経緯があります。これをシンプルにここまでまとめられるか!という印象でした。デザイナーさんの手も借りての作り上げだとは思いますが、こういうところに大手出版社の凄さを感じます。
また、マップに添えるかたちで各教科の傾向が載っています。法規であればA問題・B問題の穴埋め or 計算問題の割合が記載されていました。
テンポよく単元を消化できる
法規科目は条文のインプットが多く、とても単調になりがちです。よくある参考書では、条文の羅列→例題→解説(と言っても条文の穴埋め部分をハイライトしただけ)となります。
一方で、TACの本は
- 高圧・低圧電線間の距離のイメージ図
- 分岐盤内のイメージ図
などを使った開閉器の種類の説明を多用していて、保守者が普段何気なく見ているものを使っての説明が上手でした。
それ以外には、条文の説明の前に背景説明をして、最後には吹き出しを使ったひとこと説明があって、知識の咀嚼をサポートしてくれます。
既に売上No.1?!
TACの参考書は最近出版されたばかりで、他社の電験3種の参考書シリーズから比べると後発です。が、どうやら紀伊國屋・三省堂・TSUTAYAとかの売上データから集計した限りでは、「みんなが欲しかったシリーズ」が売上No.1となったそうです!
売上No.1※の実績を持つわかりやすい教材!
※紀伊國屋PubLine データ、M&J PBA-PROD、三省堂 本DAS-P、TSUTAYA DB WATCHの4社分合計を弊社で集計
みんなが欲しかった!シリーズの「電験三種 はじめの一歩」「電験三種 理論の教科書& 問題集」「電験三種 電力の教科書& 問題集」「電験三種 機械の教科書& 問題集」「電験三種 法規の教科書& 問題集」2019.1 ~ 2021.7(公式サイトより引用)
Amazonランキングでも「やさしく学ぶ」シリーズや「完全マスター」シリーズを押し分けて、各科目が首位グループを独占しています。
公式サイトで一部プレビューができる

公式サイトに行って「立ち読み」をクリックすると、全体をかいつまんでどのような中身になっているか確認できます。
図が豊富で、読んでて飽きさせないような仕上がりになっていることがすぐわかるかと思います。
なんと公式HPで買った方がいちばん安い?!

正誤表を調べて公式HPを徘徊していたら、凄い情報を見つけました!
なんと、公式HPで買うと10%OFFになるようです。しかも各科目の4冊をまとめてセットで買うと、15%OFFになるようです!送料もかからないですしAmazonより安いので断然コチラで書いですかね。
まとめ
ほかの参考書と違って、全体的に1つ1つの単元を丁寧に説明している印象を受けました。私が電験3種を勉強し始めたときに、これを初めから使用していれば、もう少し手際よく勧められたかなと少し残念な感じがしました。
また、原理・現象がきちんと説明されているので、これを使えば単純暗記に逃げなければならないところが少なくなるかと思います。逃げるとしても、記憶の切っ掛けがたくさんあるので単純暗記にそれほど苦労しないはずです。
参考書学習を含めた全体的な電験3種の勉強の流れとしては、
- 参考書を仕上げてベースを作り
- あとは問題集で過去問の数をこなす
なるかと思います。ということで、TACさんが過去問題集を出せば全て出揃う感じです。
出さないんですかね笑 ここまでくると気になります。
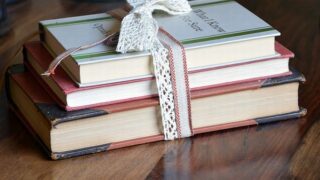
それでは次回!